受動喫煙防止は、マナーではなくルールです
市内の学校は夏休みに入り、子どもたちが日中地域で過ごすことが増えます。
20歳未満の人や妊婦、患者等は、たばこの影響を受けやすいと言われています。喫煙は自分だけの問題ではありません。周りにも影響を及ぼすことを今一度確認ください。
受動喫煙とは

たばこを吸っていない人が、たばこを吸っている人の吐き出す煙や、そのたばこから出る煙にさらされることを受動喫煙といいます。吐き出す煙にはもちろん、たばこから立ち上る煙にもタールやニコチンなどの多くの有害物質を含んでおり、喫煙者だけではなく、非喫煙者の健康にも影響を及ぼしています。
受動喫煙による健康被害

受動喫煙との関連が確実とされる病気は、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群があります。この受動喫煙に関連した4つの病気により、年間約1万5千人もの人が亡くなっているといわれます。また、鼻腔がんや乳がん、喘息、COPD、胎児発育遅延などさまざまな病気のリスクを上げる可能性もあり、受動喫煙による健康への影響は深刻な状況です。
受動喫煙防止はルール
受動喫煙による健康被害の現状から、望まない受動喫煙防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設などの管理について権原を有するものが講ずべき措置などについて定める「健康増進法の一部を改正する法律」が2020年に施行されました。受動喫煙防止対策はマナーからルールへと変わり、違反者へは罰則も設けられています。
改正法の基本的な考え方
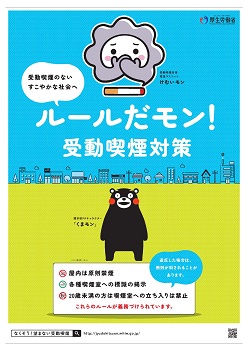
(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
(1)~(3)をふまえ、以下のことがルールとなっています。
- 多くの施設において室内が原則禁煙
- 20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入り禁止
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
- 喫煙室には標識掲示が義務付け
受動喫煙対策の施設区分
学校、病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、、施術所(はり、きゅう、柔道整復)児童福祉施設、母子健康包括支援センター、行政機関の庁舎など
*屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙所を設置できる。
<必要な措置とは・・・>
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
- 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、旅客運送用船舶、裁判所など
*個人の自宅やホテルの客室など、人の居住する場所は適応外。要件を満たし規模の小さな飲食店は経過措置があります。
喫煙を主目的とするバーおよびスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所
新型たばこと呼ばれる、電子タバコや加熱式タバコも一部規制がありますので、ご確認ください。
事業所の皆さんへ
受動喫煙対策を行う際の支援策があり、喫煙室の設置にかかる財政・税制上の制度が整備されています。詳細は、添付の資料を参照ください。
- 支援に関する相談窓口:天草保健所(天草市今釜新町3530)電話:0969-23-0172